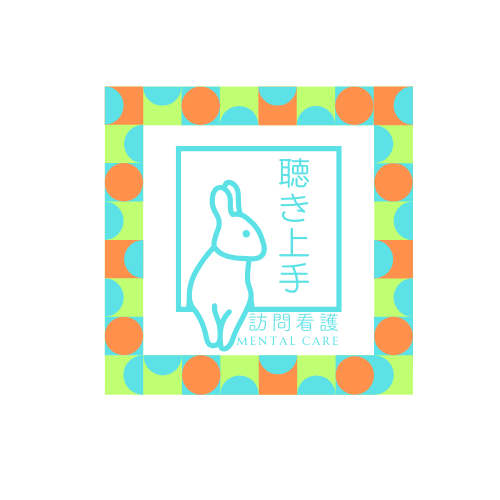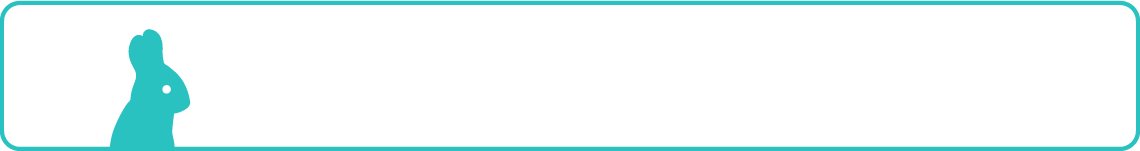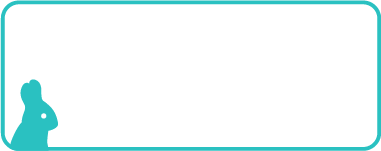精神科訪問看護全般
2025-06-05
訪問看護ってなんもしてないやん・・・・。
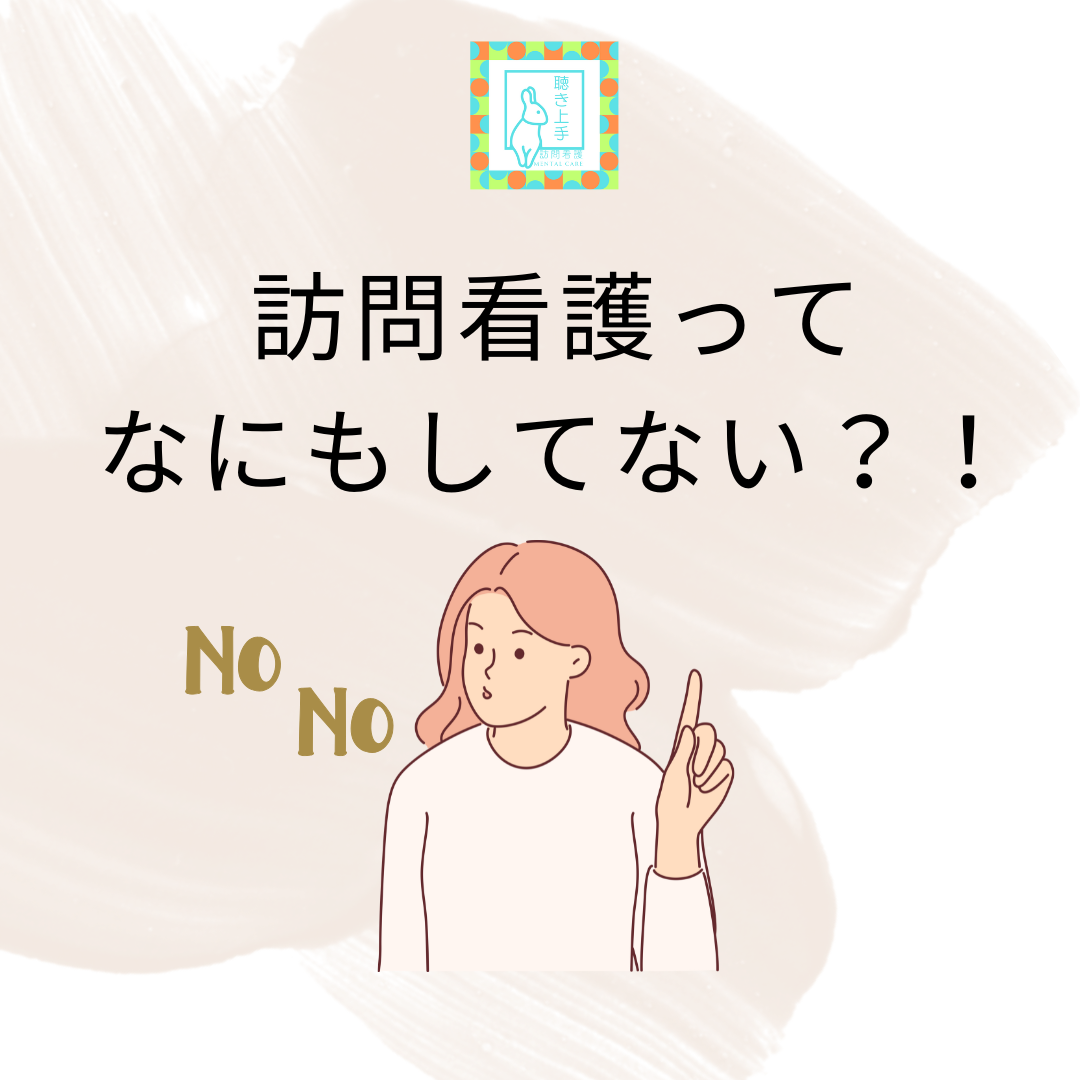
みなさんこんにちは!聴き上手です。
「“訪問看護”って何もしてないの?」
~ただ来てるだけじゃない!見えにくい仕事の中身~
先日ある方に
“訪問看護”って何してるの?ただ来てるだけ?と言われてしまいました。
あることで行き違いになって出てきた言葉なので、そのあときちんとお話をさせてもらいました。
でも、形のないケアってそう思われてしまうことがあるよな~と思い
今日はそれについて書いてみようと思いました。
■ ショック!:「ただ来て話して帰るだけ?」と思われている?
「訪問看護って何してるの?」
「話し相手になってるだけじゃないの?」
「医療行為してないなら、あんまり意味なくない…?」
そんな風に思われてしまうことがもしかしたら、あるのかもしれません。
特に精神科の訪問看護は、“目に見えるケア”が少ない分、誤解されやすい分野です。
でも実際には、ものすごく“見えにくいケア”に満ちているのが、私たちの仕事です。
この記事では、「訪問看護って何してるの?」という疑問に対して、聴き上手での実際の関わりをもとにお伝えしていきます。
■ 訪問看護=“暮らし”の観察と調整役
訪問看護の主役は、“症状”ではなく“生活”です。
食事は取れているか?
昼夜逆転していないか?
着替えられているか?
表情に活気があるか?
話のテンポや内容に変化はあるか?
個々には書ききれないくらいの観察をしています。観察というと利用者様にとっては
何か見張られているようなそんな風に捉えられることもあるかもしれませんが
平たく言うと、五感を精一杯駆使していつもと同じかそうでないのか、何が違うのかを感じています。
…これらすべて、看護師は「気にしながら雑談している」のです。表面的には「何気ない会話」でも、
その裏では膨大な観察と判断が同時に行われています。
■ 「なんとなく変」が見抜けるのがプロの仕事
精神状態の変化は、ほんのわずかな“違和感”から始まることが多いです。
前よりちょっと声が小さい
アイコンタクトが少ない
自分のことを責める言葉が増えた
話がまとまらなくなってきた
こうした小さな“ゆらぎ”をキャッチし、
本人にも気づかれないうちに「崩れる前の一手」を察知していくのが私たちの役割。
そして、これはケースバイケースですが、基本的にはご利用者様がご自身で自分のサインを
キャッチして、対応までできるようサポートしていきます。
■ 「ただ来て話してるだけ」に見えて実は…
◎ 実は:行動の意図を読み取っている
「カーテンがずっと閉まってるな」→外に出るのが怖くなっている?
「最近、音に敏感みたい」→不安が高まってきている?
目に見えること、生活の中の変化、暮らしぶりを“手がかり”に、心の状態を読み取っています。
◎ ご家族との調整や、煮詰まった家族関係に風穴を開けることも仕事
「最近、本人の元気がないんです」
「一緒に住んでるけど、どう関わっていいかわからない」
家族の疲れも、訪問でしっかりキャッチして支援につなげます。
当事者ご本人だけではなく、ご家族も支援の対象。疲れたり、迷ったり、時には怒りを抱えていたり
そんな気持ちに寄り添います。
◎ 他職種との橋渡し
医師、相談支援員、福祉施設、就労支援機関などとも連携します。
就労Bを休みがち、何があったのかなとか、言葉にならない悩みを抱えてるように見えるけどどういうサポートが必要なんだろう?
また、退院がま近になると、相談支援員さんが連絡を下さったりします。そうやって双方向に連携しながらおひとりおひとりの
暮らしを支えています。
■ “聴き上手”の訪問スタイル
私たちは、“何もしない時間”も大切にしています。
◎ 無理に話させない
「今日は話したくない」という日もある。
そんな時、ただそばで静かに過ごす・・・・・そんな時間も、大事な支援。
◎ 「どうしたい?」より「どう在りたい?」
将来の話をする時も、焦らせず、「どうなりたいか」ではなく「どんな毎日を送りたいか」に目を向けます。
リカバリー支援の主役は、あくまで本人。まず、自分のゼロベースに戻る、そうなれるという希望を持ち続けられることが大切。
そして、リカバリーできたら、一緒に次の目標を探していきます。
◎ 記録では見えない“空気”を大切に
「あ、今日はちょっと違うな」と感じる感覚を、無視しない。気になったことは必ずチームで共有し、全体で支えていきます。
■ 利用者さんのエピソードより
ある利用者さんは、初回の訪問で「何を話せばいいの?」と不安そうでした。
数ヶ月後、その方はこんなふうに話してくれました。
「看護師さんが来ることで、“あ、私、生きてていいんや”って思える日があるんです。」
一見、何もしていないように見える訪問の時間が、その人の「生きる感覚」を支えていることもあるのです。
■ まとめ:「見えにくいけど、確かにある支援」
訪問看護の仕事は、診察のように明確な処置や数値が出るわけではありません。もちろん私たちはお薬を処方することもありません。
でも、確かに“変化を支える力”があります。
「なにげない会話」の中に、安心がある
「ただいる」ことで、孤独が軽くなる
「気づく」ことが、崩れる前に支える一手になる
訪問看護師は、そっと生活に入り、そっと支えています。それは、依存関係をつくらないこと、主体性を育む関りをモットーにしているから。
だから目立たないけれど、あなたの暮らしが変わるお手伝いをしています。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。